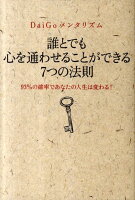春は新しい出会いの多い季節です。
コロナのせいで卒業式もなく突然離ればなれになっている現状ですが。
何かと環境が変わるこの季節には、新しい自分を出して良い人間関係を作っていきたいと考えている方も少なくないと思います。
しかしその意気込みとは裏腹に、いざ初対面の人だらけの環境に飛び込むと思い通りにいかず、自己アピールに失敗して今まで通りの地味な日常を送ってしまうなんてことはよくあります。
自分なりには明るく接しているつもりが空回りになっていて、周囲から浮いてしまったり、話が噛み合わないと感じてしまうこともあります。
しかし、会話の中でちょっとした心理学のテクニックを取り入れてみるだけでスムーズにコミュニケーションが取れるようになるかもしれません。それが「マーキング法」と呼ばれるものなどがあります。
今回は、会話の中のちょっとした工夫で印象がUPする心理学について紹介します。
「マーキング法」会話で役立つ心理学

豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
人とのコミュニケーションで興味を惹きつける心理学的な方法として「マーキング」というものがあります。
コミュニケーションにおける「マーキング」とは、直接的な表現で「私と友達になってください!」と伝えるではなく、会話中の仕草などから無意識のうちに「なんかこの人といると居心地が良いな」感じとってもらう方法です。
例えば「この仕草をすると、あいてはこういう仕草をする」「この質問をすると、相手はこう返してくれる」のような、心理学の研究を元にした傾向があります。
このような「マーキング法」を会話の中に自然に盛り込むことで、自分が期待した反応を相手がしてくれるようになるかもしれません。
1.「アナログマーキング」で会話にメリハリをつける

「アナログマーキング」とは、会話の中で強弱をつける基本的な印象付けの方法です。
大事な事や内容を人に伝えるとき、会話のトーンや大きさを変えて強弱をつけた方が頭に残りやすくなります。
強弱の付け方は、伝えたい部分をただ強くすれば良いという方法だけではありません。
時には小声で伝えることが効果的な場合もあります。
例えば授業中に先生が大事なポイントだけを突然小声で言ったりするように、敢えて抑えた方が相手が集中して聞いてくれることもあります。
▼注目を引く「マーキング法」の例
◆声量、高さ(トーン)に強弱をつける
◆話の「間」とテンポを変える
◆話している時の姿勢や仕草
◆表情と目線
例えば、注目してほしい話題の時に、特定の仕草と声の抑揚などを組み合わせると
さらに効果が上がります。
しかし、アピールしようとして力みすぎるとかえってプレッシャーとなってうまくいかないこともあります。
声が上擦ったままやテンポがやけに速い、姿勢や仕草に緊張感があるなども相手に感じ取られます。逆に印象を悪化させることもあるので、緊張していると自覚した場合は深呼吸などで気持ちを落ち着かせる行動をとることをおすすめします。
話題関連に悩む人はこういう記事もどうぞ
2.良い印象へと誘導させる「埋め込み法」

追われるとなぜか逃げたくなってしまう心理のように、直接的なアピールは程度が過ぎると逆効果で鬱陶しく思われてしまうことがあります。
「埋め込み法」とは間接的なアピール方法のことです。思わせぶりな態度を取る人は「埋め込み法」の使い方がうまい人です。
控えめの方が好感を持たれる場合もあります
本当に伝えたい直接的な表現は抑えて、思わせぶりな態度で徐々に誘導させるイメージ付けを行うことにより、相手は自覚のないまま好意を持ってくれるようになるかもしれません。
▼A子が気になるB男くんの埋め込み法の会話
(A子って料理上手らしいしなんか良いなあ)
B男「料理が上手い人(A子)っていいよね」
A子「そうなの?」
B男「もしそんな彼女(A子)だったら彼氏も嬉しいだろうな」
A子「そうなんだ」
B男「料理を褒めてくれるだろうし生活も楽しくなると思うよ」
A子「確かにー」
B男「あーあ、誰か俺にも作ってくれないかなー」
A子(・・・B男くんに作ったら私も褒めてもらえるのかな)
3.話題を敢えて脱線させる「混乱法」

学校で長々と授業を受けていると眠くなりますよね。
人は、興味の薄い話や理解が追い付かない状態が続くと脳が退屈を感じ、思考力が低下していきます。その結果、眠くなるということが起こります。
「混乱法」は、今までの話題から脈絡もない話を突然盛り込む会話テクニックです。
突然話題が飛んだり関係ない話になったとき、聞き手は「あれ?今何の話だったっけ?」と異変に気付きます。
混乱法による異変を作ることで、切れかけていた聞き手の集中力を再び高める効果があります。
学生の頃、授業中によく話が脱線する先生はいませんでしたか?
先生が「混乱法」のテクニックを意図的に行っているかは分かりませんが、授業の合間に脱線してどうでも良い話をすることは、再び集中力を上げるための効果ある方法です。
《 ポイント 》
話に注目して欲しい場合は、関係のない話題を盛り込む
4.沈黙の間を利用する「サイレントフォーカス」

複数人や大勢で話している環境だとなかなか自分の話すタイミングがつかめないという人もいると思います。それで無理矢理に割り込んで入って自分の話をしても、空気を壊してしまったりして悪い印象を持たれてしまう可能性もあります。
そんな時は敢えて沈黙をつくる「サイレントフォーカス」という方法が有効になるかもしれません。
例えば、話しかけておいて途中で会話を止めてみる、伝えたいことの前に数秒の長い間を作るなどという方法です。
これを実践すると周りの人は、話すと思っていた人が急に黙ったために「どうしたんだろう?」と不思議に思います。
そう思わせることができたら相手をすでにこちらのペースに引き込むことが出来ています。
相手の意識を動かす方法は大げさな行動だけではないという例です。
「マーキング法」についてまとめ
マーキング法をうまく利用することが出来れば、気の惹かせる方法が上手くいかなかった人でも自然な形で印象操作できるようになります。
今回紹介した「マーキング法」の方法のメリットは
コミュニケーション能力の低い人や、話が苦手な人でも実践しやすい、人の惹きつけ方だという点です。
話し方を大きく変えることなく、さりげない会話中のコツで与える印象を変えることができます。
今回の紹介した内容のまとめ
会話中の声や仕草に抑揚をつける「アナログマーキング」
間接的に好印象を与える「埋め込み法」
わざと話を逸らせて異変に気付かせる「混乱法」
狙った沈黙を作り自分に集中させる「サイレントフォーカス」
以上のマーキング法テクニックを自分の武器に出来れば、仮に面白い話が出来なくても
話のネタが少なくても、伝えたいを注目を引き付けるここだという場面でぶち込めば、
「コミュ障だ」という印象を持たれることは少なるかもしれません。
興味があれば、新しい環境での友達作り、クラスや会社の集団での印象づくり、あるいは狙いの異性にアピールしたいときなど、自分自身を紹介する場の参考にしてみて下さい。
今回、参考にさせていただきました
人間関係の心理学関連記事はこちら
ありがとうございました