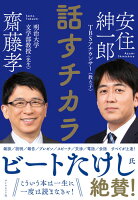自分では楽しく会話をしているつもりでも周囲からはつまらないと思われているかもしれません。
例えばオチがなくてまとまりのない話し方をしてしまう人、同じ話を何度も話してしまう人は、一緒にいてつまらないと思われることがあるかもしれません。
話題をしっかりと落とせるスキルのある人は聞いていてまとまりがあり、惹きつけられますよね。話がつまらない人とはどんな特徴の違いがあるのでしょうか。
今回は「同じ話を繰り返す人」や「話にオチのない人」の特徴、改善策対策を紹介していきます。
話がつまらないと思われる人の特徴

豆腐メンタルのとふめんです(@tohumen090031)
自分では楽しく話しているつもりなのに、つまらない、面白くないと言われたらショックですよね。
ただ相手が感じ悪いだけかもしれませんが、面白くないと言われる原因は自分の話し方にあるかもしれません。
話に必ず笑いところやオチを作る必要はありませんが、内容がまとまっていないと相手に伝えたいことが伝わらずに「何が言いたいの?」と思われてしまいます。
また、同じ話を繰り返してしまう人も、飽きられて面白くないと思われてしまいます。
それでは、どういう話し方をしているときに「面白くない」思われてしまうのか、具体的に紹介していきます。
1.話にオチがない人

テンポよく会話が出来る人や誰とでも話が出来る人はコミュニケーション力が高いので、会話に苦手意識を持っている人からすると羨ましく思います。
しかし沢山話せることが「面白い人」なのかはまた別の問題です。
話の展開や空気の流れを作るオチがないと、どんな面白い内容だったとしても聞き手が面白くない場合があります。
全ての話にオチが必要だとは思いませんが、聞き手はどうしても笑いどころや意外性を期待してしまいます。
話に展開の波もなく、オチもなく終わってしまうと、
「それで終わり?」と拍子抜けしてしまうこともあります。
原因1.内容と結論がずれている

話がいまいち盛り上がらない原因として、話のオチの有無が問題の前に話の着地点が主題から逸れている場合があります。
話す内容がうまくまとまっておらず、途中から話の内容が別の方向へ飛んでしまうと話しの構成も不自然となり、聞き手は違和感を覚えます。
例えば、人気のカフェへ行ってきた人の会話の場合
A子「昨日、美味しいってずっと話題になっていた人気のチーズケーキが気になって食べに行ってきたの!でも……」
B子「うんうん (そうでもなかったのかな)」
A子「1個1000円もしたの!」
B子「??? へぇそうなんだ・・・。(味の感想は?)」
聞き手は話の流れからどんなテーマが要点を掴み、どのような結論だったかをおおまかに予想します。
今回の場合は「美味しいチーズケーキのあるカフェに行ってきた話」です。
話の流れからして、聞きたい話は「チーズケーキの味」の感想です。
しかし、感想は「価格に驚いた話」で着地しました。
確かに意外性はあるオチですが、主題とは大きくずれた感想になっているため、聞き手としてはすっきりしない結論です。
別のオチが出てきたので話が中途半端に終わったように感じてしまいます。
あくまでも主題に沿って話していかないと面白い話にはなりにくいです。
原因2.含みを持たせるだけの話し方

普通に話をしているだけなのに、なぜいつも話し終えると微妙な空気になってしまう。そんな心当たりがある人は、大してオチも作っていないのに自分から話の展開に期待を膨らませるような話し方をしている可能性があります。
会話は話している時の感情や抑揚、テンポによって相手に訴えかけることが出来ます。
例えば
意味ありげな長い「間」を作っている
オーバーに笑いながら楽しそうに話している
深刻なことがありそうな暗いトーンで話す
以上のような話し方をすると聞き手は、何か大きな話や展開があるのだろうと期待してしまうのが普通です。
しかし、話の内容は至って普通の話で、オチもなくそのままの流れで終わってしまうと
聞き手は拍子抜けしてしまいます。
内容に合わないリアクションは行わない方が良いです。
オチのない話をする人の改善策

オチのない話を改善するにはどんな方法があるのでしょうか。
自分のなかで話をまとめてみる

人に楽しんでもらえるような会話をするには、話の流れを考えてオチをつける必要があります。
しかし普段の日常的な会話では、どんな話をするかなど決まっていないので
オチを考えておく必要はないと思います。
それよりもまずは、話したいテーマと結論が一致していることを意識することの方が大切です。
想像しやすい話の描写力を鍛える
興味を惹かせる話し方は、相手になるべくイメージのしやすい状況の説明をして想像を膨らませてもらうことがポイントになります。
実際の建物や物、その空間に誰がいて何がある、その時の自分がどんな感情でいたかなど、具体的な体験や表現をして聞き手に正しく伝える力を養うと共感を得られやすくなります。
さらには話のテンポも聞き手の興味を惹くには重要です。
テンポが遅すぎたり、間の作り方が悪いと聞き手の集中力は落ちてしまいます。
強いオチがない場合には、内容の途中で少しハードルを下げてオチに向けて話の流れに強弱をつけていくなどの工夫も一つの対策です。
話の間やテンポを意識する
無意味な間は空けない
話の強弱をつけて終盤にかけて高めていく
以上のことを意識するだけでも強いオチがなくても話に面白さが出てきます。
イメージとしては映画のような王道ストーリー、どん底から大逆転の展開
いわゆるシンデレラストーリーが惹きつける構成です。

2.同じ話を繰り返す人の特徴

同じ話を同じ人に何度も話してしまう人がいます。単純にだれに話したか忘れているという原因もありますが、自分の話は面白い、あるいはその話の内容には自信がある傾向があります。
しかし実際には自分が自信を持っているほど周囲の反応は良くない可能性があります。
表向きはみんな話を聞いてくれているけど裏では「つまらない人」と言われる可哀そうなタイプです。
そしてそう思われているのは男性が圧倒的に多いです。
最近、家族が冷たい気ような気がしているお父さん、大丈夫ですか。
原因3.自分の話が多い

同じ話を繰り返ししてしまうようなタイプの人にはいつくかの傾向があります。
それと同時に同じ話をする人は自分の話をする比率も高い特徴があります。
その理由としては次のような理由があります。
「話すことが好きで、会話をすることで気持ちが安定する」
「理解してもらっているか不安になるため、事細かに話す」
一般的に男性は女性よりも表情や仕草から相手の感情を読み取ることが苦手なので
話の辞めるべきタイミングに気付くことが出来ません。
これが男性の方が「自分の話ばかり」と思われる人の多い原因です。
原因4.受けが良いネタだから

「またこの話か」と思われて煙たがられやすいこのタイプ。
周囲も仕方なく聞いてあげている可能性があります。
同じ話をしてしまう人には次のような原因があります。
例えば
◆誰に話したかを細かく覚えてなくていろいろな所で同じ話をしている。
◆話は好きだけど話題に幅がなく似たような話ばかりになってしまう。
よくあるのが、過去にある1つの話題で話したときに笑ってもらえてとても受けが良かったというそのとき体験が記憶に残ります。
そんな過去の経験から、次も同じような成功体験を繰り返したい
または注目されたい、認められたいという欲求に縛られすぎて何度も同じ話をしてしまいます。
以上のような心理状態から
これらのパターンに気付かぬうちに嵌ってしまうのです。
同じ話をする人の改善策

同じ話をしてしまう人は、自分が好きな人や鉄板のネタが決まっているような人がやってしまう傾向があります。
このような話し方の癖は自分で気付かないことが多いので、他人から指摘されて気付くことがあります。
同じ話を繰り返ししてしまうことを意識的に直していくことは難しいですが、改善策はあるので紹介します。
1.新しい情報収集をする
同じ話を何度もしてしまう人は、過去の印象に残っている記憶をいつまでも話続けています。そこで新しく情報を取り入れたら、頭の中の情報も更新されて同じことばかり話すということも少なく出来ると思います。
例えば今まで自分が知らなかった分野を学んでみたり、ニュースなどから新しい情報を積極的に取りいれてみると新鮮な話を披露できるようになります。
2.過去の記憶を整理してみる
同じ話を何度もしていると、何度も頭の記憶から掘り起こされているので余計に記憶に残りやすくなります。脳内の引き出しの中でも取り出しやすい場所に入っているので、話したいと思った時にすぐ出せてしまいます。
同じ話ばかりすることを避けるための方法として、一度ゆっくりと過去の記憶を振り返ってみるのも良いと思います。
落ち着いた時に過去の記憶を思い返してみると、奥の引き出しに眠っている、忘れていた記憶が思い出されるかもしれません。
思い出したことをノートに書き出してみると整理しやすくなります。
オチのない話や同じ話を繰り返す人の特徴を紹介しました。
興味がある内容があれば是非、参考にしてみてください。
参考にさせて戴きました。ありがとうございました。
コミュニケーション関連記事はこちら
ありがとうございました。